田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」 タルマーリー発、新しい働き方と暮らし
「気づけば定職にもつかぬまま、30歳になろうとしていた。どんな小さなことでもいいから『ほんとうのこと』がしたい。初めて自分の心の奥底から出てきた、その声に従い、僕はパン屋になることを決めた」マルクスと天然麹菌に導かれ、「田舎のパン屋」へ。そこで実践する、働く人、地域の人に還元する経済と暮らしが、いま徐々に日本社会に広がっていく。ビール造りの場を求め、さらに鳥取・智頭町へ。新たな挑戦を綴った「文庫版あとがき」も収録。
おすすめポイント
- ☑パン屋がここまで考えるか!
意見をちゃんと持ったパン屋。こうしたパン職人の考えのおもしろさを知ると同時に、30代になってパン屋の目標に向かって動き出したことを知ると、僕ら20代はまだまだ遅くないんじゃないかって感じさせられる。いけるぞ、僕ら!まじでマルクスの資本論のロジックをパン屋にあてはめ始めたあたりからおもしろさが暴走していた。めちゃめちゃためになる。岡山の真庭市にある「タルマーリー」行ってみたいし、すこし働いてみたいな。
田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」 タルマーリー発、新しい働き方と暮らし
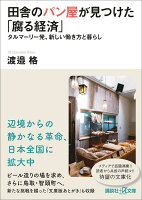
世の中、学生くさい正論だけでは成り立たないんだよ
- 野菜の卸売業者で働いているときに黒を白にしなければいけない理不尽な社会の現実を知った
- 今でも「おかしいものは、おかしい」という軸がある
夢に祖父が出てきて「パン屋をやりなさい」みたいなことを言ったとかいうのはよくわからん。 そんなこと現実にほんとにあって、それが人生に大きな影響を与えるような結果をもたらすのなら、僕はまだそういった夢のお告げを経験したことがないんだなあ。いつか起こるのかな。
天然酵母っていいんですか?
- イーストと酵母の違いについてかつての同僚のTさんがわかりやすく解説してくれていた
- 「酵母」っていっても個性がある
- たとえばでんぷんが好きだとかタンパク質が好きだとか、酸性に強いとか弱いとか、水分に強いとか弱いとか
- 天然酵母はそうしたいろんな種類や性格の酵母が含まれている
- イーストはその中から製パンに向いた酵母だけを選び出して人工的に増やしたもの
- 栄養たっぷりの培養液の中で酵母を増やしたり
- 酵母の改良に薬品や放射線を使ったり
- こうした培養の仕方を問題としてイーストを危険視している人もいる
- イーストによって誰でも簡単にパンを発酵させるようになってパン屋の形態も変わった
- かつては発酵技術はパン屋の職人の秘伝の技で暖簾分けしていくものだった
- いまではパン屋の経営や労働の形を大きく変えた
- 資本家と労働者、超効率主義という資本主義的な雇用関係がパンに広がっていった
- 「酵母」っていっても個性がある
「技術革新」で経営者の「利潤」が増える資本主義のロジック
-
マルクスは生産性が向上すると資本家の利潤が増える
-
労働力の「交換価値(給料)」は1時間にどれほどのパンがつくれるかが1つの因子となる
- イーストによる生産性の向上によって1時間の労働で倍のパンを作れるようになったとする
- すると全体の労働時間は同じ時間で労働者に支払うコストは変わらずに売り上げを向上させることができる
-
労働者の給料「交換価値」は技術革新によって増えないのだろうか
- マルクスによると技術革新はけっして労働者を豊かにしないどころかより資本家が労働者を支配する手段となる
- 実際は「技術革新」によってパンの価格が変わってしまう
- 「商品」の「価格」は「交換価値」によって決まる
- つまり「労働時間」による
- したがって、技術革新でパンの製造効率が2倍になったらパンの「交換価値(価格)」は半分になっているはず
- しかし、ある条件の下では技術革新語も以前とあまり変わらない「価格」で「商品」を売ることができる
- その条件は、新しく開発された技術を、限られた特定の資本家だけが売っているという条件
- こうして先んじて「技術革新」に成功したパン屋は大きな「利潤」を得られる
- けれども、実際の資本主義社会は熾烈なため、新しい技術を手にした資本家は「価格」を下げるかもしれない
- これはより多くのシェアを得るためである
- さらに、同じ技術レベルに追いついた同業他社に追い打ちをかけるためにさらに「価格」を下げて、結局はじめの「交換価値(価格)」の半分に落ち着く
- こうした結果、資本家の得られる利潤は結局もとと同じになってしまう
- しかし、淘汰した同業他社のシェアを得ることにより若干の利潤を得られる可能性は高くなる。
- マルクスによると技術革新はけっして労働者を豊かにしないどころかより資本家が労働者を支配する手段となる
技術革新によって最後に笑うのは誰だ?
- 資本家にとって「技術革新」によって大きな「利潤」を得られるのは一瞬でしかないことが先ほどの例で分かった
- しかし、「労働者」にとっては同じパンを半分の「価格」で買うことができるのは朗報ではない
- 「労働力」の「交換価値」を決めるのは生活費と技術習得費と家族の養育費の合計額を基準に決まる
- 「商品」の「価格」が安くなれば生活費も養育費も安くなるため給料は下がる
- さらに「技術革新」によって技術習得費が下がる
- さらにさらに労働が単純化することで「誰でもできる」仕事によって「労働者」の価値、立場はさらに弱くなる
マルクス風に言うと
労働者は機械の単なる付属物となり、こういう附属物として、ただもっとも単純な、最も単調な、最もたやすく習得できるコツを要求されるだけである」
消費者目線で考えると「商品」が安ければ安いほど、ありがたく感じられる。 もちろん、経営者目線でも安いほど売れるという思いはつねにある。
しかし、こうした考えが労働者の首を絞めることをマルクスは示している
こうした悪循環から抜け出すために、 「タルマーリー」では
- 厳選した食材を使い、
- 手間暇をかけて
- しっかりとパンを作る
- 対価としてまっとうな価格をつける
- パン職人の技術を活かしたパンをパンを作り続けられるようにしっかり休む
「小商い」の大切なポイントは「利潤」を追求しない
- 「利潤」を生まれる仕組みは労働者に払う給料より生み出したものを吸い上げることから生まれる
- このため労働者にきっちりと渡せば利潤とは無縁でいられる
おわりに
もちろん、この本に出てきたマルクス主義の内容がすべてではない。実際に技術革新が私たちの生活をより豊かに、多くの余った時間を活用できるようにしてくれたのは言うまでもない。
ただ、売れ残ったパンを従業員にあげない。 といった資本主義はほんとうに悲しくなる。
タルマーニの姿勢はほかのパン屋だけじゃない、すべての経営者が知るべき考えなんだ。
