鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。
出張先は火山にジャングル、決死の上陸を敢行する無人島だ!知られざる理系蛮族の抱腹絶倒、命がけの日々!すべての生き物好きに捧げる。
おすすめポイント
- ☑書いている内容はいい
- ☑おじさんののりがうざすぎて紙面の半分以上を余計な情報が占めている
鳥のことが好きな鳥類学者が書いている本。 鳥類学者が少ない上に、彼らはコミュ障なことが多いと書いてあったが、この人はコミュ障だろうか? 内容自体は面白いはずなのに余計なユーモアがたくさんあるけれども、僕には彼のユーモアセンスが欠けているようにしか感じられなくなって辛すぎてやめた。文章だけで人を生理的に嫌いにさせることができるのはある意味一つのセンスだと思う。あるまじき文才おそるべし! なんて思っていたが、鳥に関する話はおもろいし、たまには真面目なことを言う。最後の方には彼のユーモアセンスがわかりはじめてきた?じゃあ読み返して確かめてみる?、なーんてそれはしないかな
鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ
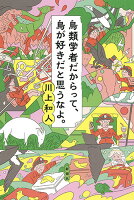
鳥類学者には絶海の孤島がよく似合う
メグロ、メジロの仲間で小笠原諸島の母島列島だけに生息している。 第1章はメグロの話。
メグロの生体系の話よりも、東京都の鳥がユリカモメになってしまっていることにたいして憤慨している話の方が多めだ。 ただ、これが決まったのは小笠原諸島がにほんにへんかんされるまえだったらしいのでしょうがないしょうがない そんなことしている暇あったら他の施策を改善したまえ東京都よ!
鳥類学者、絶海の孤島で死にそうになる
前章でも、夜中鳥の鳴き声を聞いたら外に出るために、耳栓をせずに寝ることが多いと書いてあったが、そうしたら蛾が耳の穴に入って激痛が走ったというきもちわるいたい話をしていた それよりも死にそうになることなんてあるのか大丈夫か、鳥類学者
南硫黄島という日本で最も自然が保護されている地域の一つへ訪れた時の話。 生態系を壊さないために持っていく物資やら一つ一つを消毒していく裏舞台の話が詳しく書いてあって面白い。
島に入る1週間前から種子のあるフルーツを食べることを禁止するっていうのは、思いつかなかったので面白い。 そこまで厳格か! すごいぞ硫黄島
死骸の分解者(ネズミやカラスのような)がいないためそこらじゅうに死体が分解されずに残っているそう。 そして蝿が多い
おもしろい、死ぬ思いのストレスやハエ、落石などと格闘して帰ってきたと思ったら、NHKのテレビドキュメンタリーで放送されていた内容に驚いたそう。 なんだか「美しい島」として紹介されていて笑ったそう。 テレビの風景は、真実の一部でしか無い
偏愛の章
割りと真面目なことをいう、生態系保全の裏にある事実
ヤギはクレージーでどんなところでもいきぬいていけるらしいので、かつての船乗りは島を見つけるたびに食料確保のために放し飼いにして置いてきたらしい そのせいで彼らが今、シマノ生態系を破壊しまくってしまった。
生物多様性を守るためにはヤギを駆除しなければならないが、やっぱり痛ましい。 「生物多様性」を守るためには何かしらの「犠牲」がいるのかもしれないって、知っておくのは大事なことだよね。
放置するのは容易いが、目の前で進化の歴史性が失われていくのを見過ごすことはできない。 何もしないことは現状維持にはならないのだ。研究者は殺しを推奨し、担当者は文字通り血と汗に塗れる。 環境保全というきれいな言葉の裏にある泥臭い現実を忘れてはならない。
p.80
ヤギの駆除によって、話は終わり、、、とは行かないのが生態系の難しいところ
ヤギを駆除したことによって新たな脅威が湧き上がってきてしまっている。 たとえば、外来植物。 今までは在来、外来問わずに食べまくってきたヤギさんがいたものの、いなくなってからは厳しい植物同士の戦略勝負。 外来植物のタフさに負けて、在来植物がオーストラライア原産のトクサバモクマオウや中南米原産のギンネム 国内外来のガジュマルやシマグワ、シマサルスベリなどが瞬く間に空き地に侵食した。
増えたのは植物だけではなく、動物のクマネズミ(外来)も増加したと言われている。 ヤギがもちろんネズミを食べるわけではない。 ヤギがいなくなったことによって植物が増え、食料が増えたことによる増加と見られている。
これを駆除するのは難しいだろうし、駆除したら次は何が増えるのだろうか?
鳥の外見は、バードウォッチャーが識別しやすいように進化するわけではない。
p.92
おわりに
けっこう読み進めるのがきつい本で(久しぶりにこんな本に出会った) 飛ばし読みする部分も多かったのだけれども、「研究」っていうイマイチよくわからないワードを一般の人向けにわかりやすく説明してくれたところがこの本のおすすめできるところだ。 そして一般向けだけでなく、将来の研究者志望、学生で論文を書こうとしている人たちにも「研究」っていうのは、「研究者」っていうのはこういう事を考えたり、つらいことをしたりして生きているんだよっていうことを伝えてくれている。
英語ができそうに見えて全くできない下りはとてもおもしろく、笑っているだけでなく僕ら若い世代は本気でがんばらなきゃなっていう話題ではあるのだけれども、こうしたユーモアがようやくわかりかけた頃にこの本は終章になってしまった。 残念(?なわけ)
リンゴジュースって何色?
「マズそっ!リンゴっつたら、赤だろうが!」
p.194
たしかになw
ようやくまじであんたのユーモアでくすっと笑えるようになったよ
おわりに、では
「オワリニ」では、彼の今までの人生がかるーーーく紹介されている。
断るのにエネルギーが必要でつねにイエスと答え続けたために鳥類学者になってしまった…
でも、研究者としては成功している方で多分性格が良くて頭がいいんだろう
長いものには巻かれろ。の精神も。大事なんだよねぇ
