魚ビジネス
ビジネスパーソンが知っておきたい「教養としての魚」。
おすすめポイント
- ☑魚のビジネスを幅広く知りたい人へ
- ☑魚を食べるのが好きになる
「これからの日本は、世界は、”魚”の知識がワインと同じくらい一般教養として必要になってくる。その可能性もあながち低くないと感じさせるとともに、肉ではなくて魚を食べるということを僕らが誇りを持ってやっていくのが大切だということを感じた点で新鮮だった。
魚ビジネス
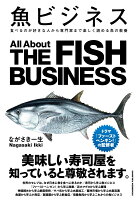
ウニ
ウニの味は鮮度ではなくミョウバンが決める。
一見、変な話だが、ウニは特に鮮度が大切なのだがすぐに品質が悪くなってしまう。
そもそも可食部はウニの生殖器なので酸化が進みやすく腐りやすい。
これを防ぐために寿司ではミョウバンを使って臭いを防いでいる。 やすいウニだとミョウバンの苦味や独特の匂いで味をだめにしてしまうが、絶妙に使うと産地のウニでも、塩水を使って時間をかけたウニでもなく、ミョウバンを使ったウニが一番おいしい。
漁業法の改正
- 2020年12月、漁業法が70年ぶりに改正された
- 改正内容は主に漁業に関する部分であるが、流通や食文化・海上利用に影響を与えるかもしれない
改正された点は
- 資源管理方法
- 界面利用方法
- 密猟対策の強化
とくに資源管理方法で変わった部分が大きい。
水産資源管理方法
- インプットコントロール: 漁業権を設置して、漁船の数や大きさを制限 => 魚をとる機会を管理する
- テクニカルコントロール: 網目の大きさ、禁猟区などの制限 => 漁獲の効率性・可能性を管理する
- アウトプットコントロール: 魚をとっても良い量を計算して定める => 漁獲量を数字で管理する
イメージでは 1 x 2 x 外的要因 = 3 (漁獲量)
今回の資源管理方法の改正によって日本は(3)の規制に変えていく方針がとられた。 それまでは1や2の方法での管理が主流だった。
アウトプットコントロールのデメリット
- コストがかかる: 科学的に資源量を調査、漁獲量を算定するのに莫大なコストがかかる
- 信頼性: そもそも科学的な結果が正しい可能性はない
- 多様な魚種を捕獲する漁法には向いていない: 1つの種の数を保全するのには効果的だが、食物連鎖の関係上にいる他の魚の保全等を考慮することが難しい
また、アウトプットコントロールはノルウェーで盛んに先進的に導入されているが、ノルウェーは国内市場が大きくなく、冷凍魚を輸出する産業がメインであることにも注意が必要。
ノルウェーのような大規模単一魚種の漁法に適した資源管理であり、日本に直接導入することができない。
その理由として、生の鮮魚市場が発達している日本では魚の値段はその日の入荷量で決まり、良い魚であっても供給量によって値段が左右される。 出荷調整がしやすいために価格を安定的に操作しやすい冷凍魚とは根本的に違う部分もあるというところに注意しなくてはいけない。
海面資源利用法
海面資源利用法と資源管理法によって小規模漁業者を実質的に潰すことができてしまう。
現にノルウェーでは小規模漁業は少なくなっていたり、イギリスでも小規模漁業者が多い中でのアウトプットコントロールの運用は困難があったりした。
「資源管理を個別の現場にあった形で調整して運用していく」ことが切実に求められる。
近大マグロは完全養殖
完全養殖は「卵」から孵化させるところまで全て自然資源に頼っていない。
1970年に国がクロマグロの養殖プロジェクトを初めてから30年の歳月をかけて完全養殖に成功した。
今では孵化後10日以内の生存率を40~60%にまで上昇させた。
関連会社のアーマリン近大が運営する飲食店「近畿大学水産研究所」@東京/大阪 で食べられる
メモ
- 生殖器が発達しない「三倍体」は栄養を実の成長に全て当てることができるのでよく育つ。「信州サーモン」などのブランドサーモンに使われている
- 締め方は一番手間がかかるのは血抜きや神経締め
- 東京都台東区御徒町駅前の「吉池」」という創業100年を超える総合食料品店の魚売り場は伝説級の人気を誇る
- クリオネやブドウエビといった品揃えの他、
- 物腰柔らかな"魚屋"のイメージとは違う店員さんが多いのも特徴
- 魚肉の細胞培養は常温下で行うことができるため、低温下で行う必要のある家畜肉と比べてエネルギー的な部分でのコストダウンと脱炭素の両面で非常に期待が高い
サバ缶ブーム
2000年代はそこまで人気の高くなかったサバ缶は今や、魚缶ナンバーワンの売上を誇る立ち位置となった。
第一次サバ缶ブームは2013年、テレビで「ダイエットに良い」と紹介されたことがきっかけ。 女性という新たなターゲットを掴んだ結果、おしゃれなサバ缶の方向性の市場が徐々に拡大していった。
第二次サバ缶ブームは2016~2018年頃。洋風の食べ方やワンパンパスタなどで使える幅や手軽さが人気となり、2018年にはぐるなび総研が選ぶ「今年の一皿」に選ばれた。
さらに第三次サバ缶ブームはコロナ禍で飲食店自粛や引きこもり需要から増えていった。
練り物
かまぼこは遅kとも平安時代からあったが、今の形とはやや違いちくわに近い形をしていた。 この形がガマ(蒲)に似ていたため蒲鉾と言われるようになったとも言われている。
蒲鉾は各地で作られているため、正確な低ギアなく様々。 使われる魚はグチやエソ、いとより、すけとうだらなどの白身魚に加えて、イワシ、サバといった青魚など。 そこに調味料の塩、みりん、砂糖、デンプンなどを混ぜる。
小田原かまぼこのように蒸して加熱する他、仙台の笹かまぼこや青森県の焼き竹輪のように焼く方法、鹿児島のさつま揚げのように挙げる調理方法もある。
カニカマ
今や世界的な人気商品となっている「カニカマ」は1972年に石川県のスギヨによって開発された。
代替肉が今後より一層トレンドとなりそうな中で、そのパイオニア的成功例。
